【企業向け】2024年にフリーランス保護新法が施行!フリーランスを受け入れる際に理解しておくべきポイントを解説
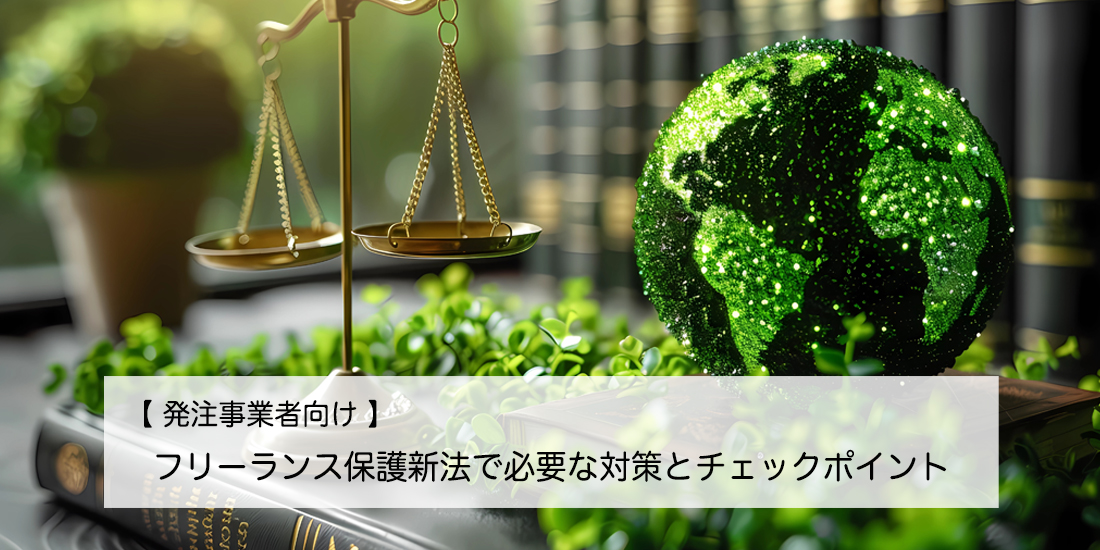
2024年11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行予定です。通称「フリーランス・業者間取引適正化法」や「フリーランス保護新法」とも呼ばれ、フリーランスに業務委託をしている事業者には法律の正しい理解と、適切な対策が求められます。
発注事業者として、今後はどのような内容を守り、気をつけなければならないのでしょうか。法律が施行された背景とともに、わかりやすく解説します。
【目次】
1. フリーランス保護新法とは?
1-1. フリーランス保護新法の概要と目的
1-2. フリーランス保護新法の適用範囲
2. 今後、フリーランスとの協業で必要になる対応
2-1. 書面などで取引の条件を明示する(第三条)
2-2. 報酬の支払期日を定める(第四条)
2-3. 禁止事項を守る(第五条)
2-4. 正確な募集情報を掲載する(第十二条)
2-5. 出産や育児、介護に対して配慮する(第十三条)
2-6. ハラスメント対策をする(第十四条)
2-7. 中途解雇などの事前予告と理由の開示をする(第十六条)
3. 従業員の有無と業務委託の期間によって適用範囲が変わる
3-1. 従業員を使用していない場合
3-2. 従業員を使用している場合
3-3. 従業員を使用しており、一定期間以上行う業務委託の場合
4. 違反するとどんな罰則がある?
5. そもそもフリーランス保護新法はなぜ制定された?
5-1. フリーランスと企業間でのトラブルが相次いでいた
5-2. 下請法では多くのフリーランスを守りきれない
6. 疑問を解決!フリーランス保護新法Q&A
7. まとめ
フリーランス保護新法とは?
フリーランス保護新法の概要と目的
フリーランス保護新法の目的は、大きく2つです。一つは、フリーランスと、フリーランスに仕事を依頼する発注事業者の取引を適正化すること。もう一つは、フリーランスの就業環境を整備することです。
本法律は2023年4月に成立し、2024年11月1日からの施行が決まっています。第一章から第五章まで項目があり、企業などの発注事業者がフリーランスに業務委託をする際に、さまざまな規制が適用されるようになります。
フリーランス保護新法の適用範囲
一言に「フリーランス」「発注事業者」と言っても幅広く使われる言葉ですが、フリーランス保護新法が適用される対象は明確に決まっています。
■ 適用対象となるフリーランス
厳密には「特定受託事業者」と呼ばれます。「一人で仕事をしているフリーランス」が保護対象で、以下の条件が当てはまります。
| ・ 従業員を雇っていない個人事業主 ・ 役員や社員がいない法人 |
上記の通り、法人でも一人社長ならフリーランスです。また、副業で働いていても従業員がいなければフリーランスに該当します。
もしもフリーランスが従業員を雇った場合は、フリーランス保護新法の対象外です。業務の途中でフリーランスが従業員を雇うこともあり得るため、契約の際は表明保証条項に「従業員を雇った場合の申告義務」を入れておくと安心です。
■ 適用対象となる発注事業者
厳密には「特定業務委託事業者」または「業務委託事業者」と呼ばれます。個人・法人を問わず、フリーランスに業務委託をする事業者はフリーランス保護新法を守らなければなりません。
■ 適用対象となる取引
発注事業者からフリーランスに発注される、業務委託全般が対象範囲です。具体的には物品の製造・加工、情報成果物の作成、役務の提供など。「情報成果物」とは、プログラムや映像、音声、文字・図形などで構成される幅広い内容を指します。
フリーランスエンジニアが企業から依頼されて行うシステム設計やプログラミングなどの業務も、業務委託に含まれます。
今後、フリーランスとの協業で必要になる対応
フリーランス保護新法の施行によって、発注事業者はフリーランスに業務委託をする際に7つの対応が必要になります。
法令(※1)に明記されている第三~五、十二~十六条までの内容が該当するので、一つずつ見ていきましょう。
書面などで取引の条件を明示する(第三条)
フリーランスと取引をする際は、書面や電子データなどで以下の発注条件を明示する必要があります。
| 【取引の条件】 |
| ・業務内容 ・報酬額 ・支払期日 ・発注事業者とフリーランスの名称 ・業務委託をした日 ・給付を受領または役務提供を受ける日 ・給付を受領または役務提供を受ける場所 ・検査完了日(検査を行う場合) ・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金払い以外の場合) |
電子データで明示する場合は、メールやSNS上の文面でもOKです。ただし、フリーランス側から書面で提示するよう求められた場合は、原則として書面を作成しましょう。
報酬の支払期日を定める(第四条)
報酬の支払期日に関しては、業務が完了した日や成果物を納品した日などから起算して、60日(2か月)以内のできるだけ早いタイミングで設定する必要があります。60日(2ヶ月)以内であればいつでもOKですが、できるかぎり早い日付にしましょう。
もしも支払期日を決めていなかった場合は60日(2ヶ月)後が自動的に支払期日とされ、報酬の支払い義務が発生します。
また業務をフリーランスに再委託している場合は、再委託であることや元委託の一定の情報をフリーランス側に明示したときは、元請けの支払期日から30日(1か月)以内のできる限り早い日付が支払期日となります。
禁止事項を守る(第五条)
フリーランスに対して正当な理由のない以下の7つの行為が禁止されるため、違反しないよう気をつけましょう。
| 【禁止事項】 |
| ・給付の受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・フリーランス側に物品を購入させる、業務に関係する物を利用させる ・経済的な利益を提供させる ・給付内容を不当に変更・やり直しさせる |
正確な募集情報を掲載する(第十二条)
雑誌や新聞などの広告でフリーランスを募集する場合、内容に虚偽や誤解がないようにしなければなりません。また、正確かつ最新の情報を保つようにしましょう。
出産や育児、介護に対して配慮する(第十三条)
フリーランスが出産や育児、介護などと業務を両立できるように、配慮をする必要があります。
例えば子供の急な発熱で納期が遅れる場合は納期を繰り下げる、介護が必要な曜日はリモートで就業するといった調整が該当します。どうしても配慮ができない場合は、理由を説明しなければなりません。
ハラスメント対策をする(第十四条)
セクハラ・マタハラ・パワハラなど各種ハラスメントを防止するために、必要な体制を整備しなければなりません。体制整備の段階は大きく以下の3ステップに分けられます。
| ステップ① ハラスメント禁止に関する方針の明確化と周知・啓発 ステップ② 相談や苦情に対応するための窓口などの設置 ステップ③ ハラスメントが発生した場合の規則や対応マニュアル、研修の整備 |
また、ハラスメントに関してフリーランス側から相談を受けたことを理由にした、業務委託の契約解除や不当な扱いは禁じられています。
中途解雇などの事前予告と理由の開示をする(第十六条)
フリーランスとの契約を途中で解除する場合は、少なくとも30日前までの事前予告が必要になります。また、フリーランス側から契約解除の理由について聞かれた場合は、原則としてただちに開示する必要があります。
ただし、災害など予告が困難な場合は除きます。
従業員の有無と業務委託の期間によって適用範囲が変わる
以上のようにフリーランス保護新法にはさまざまな義務項目がありますが、発注事業者側が「従業員を使用しているかどうか」と「業務委託の期間」によって、適用範囲が大きく変わります。
ここで言う「従業員」とは、「週労働20時間以上かつ、31日以上の雇用が見込まれる人」を指します。1日限りで手伝ってもらった場合など、一時的に発生した雇用は「従業員を使う」とはみなされません。
従業員を使用していない場合
前述した「書面などで取引の条件を明示する(第三条)」のみ、義務が発生します。
自身が一人で働いているフリーランスで、別のフリーランスに業務を委託する場合もこの範囲が適用されます。
従業員を使用している場合
「書面などで取引の条件を明示する(第三条)」「報酬の支払期日を定める(第四条)」「正確な募集情報を掲載する(第十二条)」「ハラスメント対策をする(第十四条)」が義務となります。
従業員を使用しており、一定期間以上行う業務委託の場合
<従業員を使用している場合>の内容に加え、業務委託の期間に応じて以下のように適用範囲が区分されます。
| ・1ヶ月以上の場合 「禁止事項を守る(第五条)」が義務となります。 ・6ヶ月以上の場合 「出産や育児、介護に対して配慮する(第十三条)」及び、「中途解雇などの事前予告と理由の開示をする(第十六条)」が義務となります。 |
ただし、「出産や育児、介護に対して配慮する(第十三条)」については6ヶ月未満の業務でも努力義務が発生します。
違反するとどんな罰則がある?
フリーランス保護新法に違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁長官、または厚生労働省からの調査や勧告を受けることになります。
勧告の上で改善がされないと刑事罰となり、罰金が発生します。
そもそもフリーランス保護新法はなぜ制定された?
新たに7つの対応するため、発注事業者は新たな体制の構築が求められるなど、少なからず負担が強いられます。しかし、フリーランスを手厚く保護する本法律は、現代において必須ともいえる内容です。その背景についても、あらましを知っておきましょう。
フリーランスと企業間でのトラブルが相次いでいた
フリーランス保護新法が制定された背景にある大きな要素の一つが、フリーランスの立場の弱さが原因で発生するさまざまなトラブルです。
実際に内閣委員会で法律案について議論された際も、取引においてフリーランスが被る不利益について焦点が当てられました。特に取り沙汰されたのが、報酬の不払いや遅延、発注書の未受領、ハラスメント、契約書の不作成などの問題です。これらのトラブルの多くは、フリーランスと発注事業者側の交渉力の格差によって引き起こされています。
下請法では多くのフリーランスを守りきれない
フリーランス保護新法と同じく、弱い立場の事業者を守る法律としてはすでに下請法が存在しています。しかしこれは、「資本金1000万円以上の事業者が資本金1000万円以下の事業者に発注する場合」など、適用ケースが限られていました。「資本金1000万円以下の事業者とフリーランス」の取引は、規制対象ではなかったのです。また、下請法にはハラスメント防止や就業環境整備などは含まれません。
フリーランスという働き方が広まっている今、発注事業者とフリーランスが対等に協力し合うための新たな規定が必要になったのです。
疑問を解決!フリーランス保護新法Q&A
 Q. 元請けとしてフリーランスに再委託した業務が、途中で発注元から解約されるケースもありそうですが。フリーランスとの契約書にはどう記載すれば良いでしょうか?
Q. 元請けとしてフリーランスに再委託した業務が、途中で発注元から解約されるケースもありそうですが。フリーランスとの契約書にはどう記載すれば良いでしょうか?
 A. 再委託の終了の場合ですね。本来はフリーランスに対して30日前の告知が必要になります。再委託契約書の内容でリスクマネジメントをしておきましょう。
A. 再委託の終了の場合ですね。本来はフリーランスに対して30日前の告知が必要になります。再委託契約書の内容でリスクマネジメントをしておきましょう。
契約書に「発注元から委託が終了した場合、本契約は終了とする」という旨を記載しておけば、自動的に終了することができます。
または30日前の解約告知を守るため、発注元との契約における解約告知を45日にしておくのも一手です。
 Q. 依頼時に業務内容や報酬額が定まっておらず、明示できない場合はどうしたらいいですか?
Q. 依頼時に業務内容や報酬額が定まっておらず、明示できない場合はどうしたらいいですか?
 A.正当な理由があれば、必ずしも明示する必要はありません。ただし、内容が確定した時点で速やかに書類またはメールなどでテキスト化しましょう。
A.正当な理由があれば、必ずしも明示する必要はありません。ただし、内容が確定した時点で速やかに書類またはメールなどでテキスト化しましょう。
 Q. 直接発注ではなく、エージェント経由でフリーランスへ再委託するメリットはありますか?
Q. 直接発注ではなく、エージェント経由でフリーランスへ再委託するメリットはありますか?
 A.フリーランス保護新法を遵守する観点で、多数のメリットがあります。
A.フリーランス保護新法を遵守する観点で、多数のメリットがあります。
エージェントがフリーランスとの間に入ることで、契約書の作成や報酬の支払いなど、フリーランス保護新法に準じた対応を滞りなく行えます。また、エージェントを介した契約となるため、30日前の告知がなくとも、エージェントとの解除に関する契約条件に則って解約ができます。
フリーランスとトラブルがあった場合に仲介役となってもらえる点も、メリットと言えるでしょう。
最後に: より一層フリーランスを活用するためのポイント
人手不足の今、企業の力を強めて価値創造をするためにも、フリーランスの力は欠かせないものになっていくはずです。フリーランス保護新法に対応した社内体制を整えることは必須ですが、同時に効率的にフリーランスと契約するために、エージェントを活用するのもおすすめします。
例えば「Remogu(リモグ)」の場合はリモートワークの参画がメインになるため、場所にとらわれず全国の優秀な人材を受け入れられます。フルタイムではなく必要な時間だけ働いてもらうなど、柔軟な働き方も提案可能です。
フリーランス保護新法を遵守したフリーランス活用をご検討の企業様はぜひ、Remoguまでお問い合わせください。
転職ノウハウ その他の記事
もっと読む 〉-

リモートワークのセキュリティ事故は他人事じゃない!知るべき鉄壁の防御術を紹介
リモートワークのセキュリティ対策、万全ですか?時間や場所に縛られない働き方が広がり、自由なワークスタイルを多くの人が選択しています。リモートワークは地方での新しい仕事の創出にも繋がり、可能性に満ちた働き方といえるでしょう […]
-

転職市場激変!?LLMスキルで実現する理想のリモートワーク!LLMエンジニアとして知っておきたい基礎知識
LLM(大規模言語モデル)スキルを活かしたリモートワーク転職が、今、エンジニアのキャリアを大きく変えようとしているのをご存知でしょうか。 「LLMエンジニアとして、最先端の技術に触れながら、もっと自由で柔軟な働き方を実現 […]
-

リモートワークで活躍するシステムエンジニア(SE)とは?必要スキルなどを徹底解説
近年、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、リモートワークは急速に普及しました。特にシステムエンジニア(SE)は、パソコンとネットワーク環境があれば業務を遂行できるため、在宅勤務と相性の良い職 […]
-

リモートワークのフロントエンドエンジニアになるには?必須スキルから転職成功のコツまで解説
フロントエンドエンジニアとしてリモートワークで働くということは、もはや特別なものではなくなりました。この記事では、リモートワークで働くために必要なスキル、転職市場のリアルな動向、そして成功するための具体的な方法まで、網羅 […]
